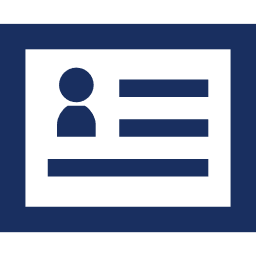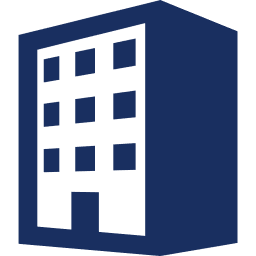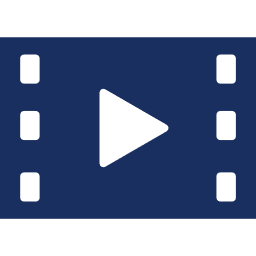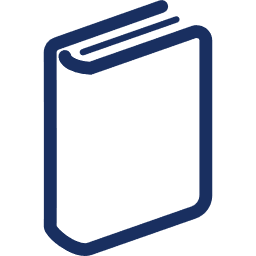ハラスメント対処法
今回は、事業主(会社)が、社員さんから職場におけるハラスメントについて相談を受けた場合の対応についてお話しします。
対応の仕方は、社員さんの相談内容に応じて二つに大別できます。一つは、被害者が名前を伏せて、加害者のハラスメントを止めさせてほしいという場合、もう一つは、被害者が名前を出してもいいので加害者のハラスメントを止めさせてほしいという場合です。
前者の場合、被害者を明らかにすることなくハラスメントの有無を加害者に追及しなければならないため、難しい対応が求められます。まず、ハラスメントの事実を立証する必要があります。第三者の証言が得られればいいのですが、そうでなければ防犯カメラの設置や音声を録音するなどしてハラスメントの現場を押さえるしかありません。どちらも現実的とはいえません。そうかといって、根拠もないまま「あなたはハラスメントをしていませんか?」と問いただすわけにもいきません。これでは、会社としてハラスメントに立ち向かいようがありません。会社としてできることは、被害者を励ましたり、管理職向けに急きょハラスメント研修を開催したりすることぐらいです。
不用意に、加害者に対して「誰からとは言えませんが、あなたがハラスメントしているという声が聞こえてきたのですが、ハラスメントをしていませんか?」などと、確かな証拠もないまま詰問してしまうと、通報者捜しが始まり、被害者は復讐(ふくしゅう)の的になりかねません。不用意なアプローチは厳に慎むべきです。
2019年1月、父親が、千葉県野田市の自宅で、小学4年の娘を虐待して死亡させるという事件がありました。この女児は、小学校で行われたアンケートに父親から虐待を受けていることを回答しましたが、学校側はそのアンケートをあろうことか加害者である父親に渡してしまい、1年後、女児は亡くなってしまいました。この事件が示唆するように、不用意に、加害者に通報の事実を伝えることは大変危険です。
ですから、どうしても加害者にアプローチする必要がある場合は、「法律によって事業主に義務づけられたハラスメント防止対策および当社の社内規則に基づき、あなたにハラスメントの事実を確認いたします」「なお、通報者に対して通報の有無を問いただしたり、どう喝したり、何らかの不利益を与えるような行為をした場合は、処罰の対象となりますので注意してください」などと、事前にきつく念押ししておく必要があります。
次は、被害者が名前を出してもいいので加害者のハラスメントを止めさせてほしいという場合の対応についてです。多くの被害者は名前を出すことに二の足を踏みます。さらに関係が悪化するかもしれないと危惧するからです。
ですから、会社は「絶対にあなたを守りますから安心してください」「もし、相手が何かしてきたら会社は厳正に処分します」などと説明して、勇気を出してハラスメントを受けたことを名乗り出ていただくように促す必要があります。
さて、名乗り出てくれた場合の対応ですが、ついやりがちな失敗があります。それは「よし!証言が得られた」ということで、加害者と面談するやいなや、厳しく責め立ててしまうことです。
しかし、この段階では、被害者の証言を得ただけであって、ハラスメントの事実関係は確認できていません。最初にすべきことは事実関係の確認です。「あなたは、こういう言動を○○さんにしましたか?」と尋ねる必要があります。ここでのポイントは、できるだけ詳細な状況説明が必要になるということです。あいまいな表現や具体性が欠けているほど、ハラスメントは否定される確率が高まります。極めて具体的に、「あなたは、○月○日○時ごろ、○○さんにこういうことを言いましたか?」と尋ねます。
相手があっさり「言いました」と認めたら、「これはハラスメントに当たりますので、二度としないでください」と厳重注意します。しかし、ほとんどのケースは、ハラスメントの事実を認めず、「本人に確かめさせてください」と言い出します。こうなると、証拠の映像や音声でもない限り「言った、言わない」「やった、やらない」の水掛け論になります。
しかし、会社は「そうは言っても、被害者がハラスメントをされたと申し出ている以上、本当はハラスメントをしているんじゃないのか!」などと糾弾してはいけません。それをしたら、会社がハラスメントで訴えられかねませんので注意してください。言葉遣いや語気に気をつけて、丁寧な口調で「そうですか。では、あなたがハラスメントを認めなかったということを相手にお伝えします」「ただし、相手を問いただしたり、不利益を与えたり、どう喝したりする行為は絶対にしないでください」「あなたはハラスメントをしていないと言いますが、あなたの行為をハラスメントと受け取る人もいることを覚えておいてください」とくぎを刺します。
会社はここまでしか対応できません。しかし、抑止力にはなります。もし実はハラスメントをした人なら、自分の身に不利益が生じかねないことを知り、以後の言動を自重するようになります。
また、会社はハラスメントの訴えに対して、おざなりにすることなく、社員さんを守るために対応することを社内に周知できます。こうした実績を積み重ねることで、ハラスメントは減っていき、働きやすい職場環境になっていくと思います。
いちばん重要なことは、経営がハラスメント問題から逃げずに、腹をくくって立ち向かうことです。それが、最大の解決方法だと思います。