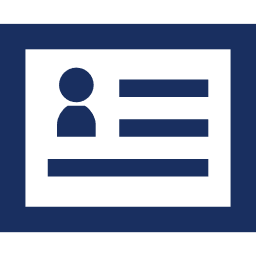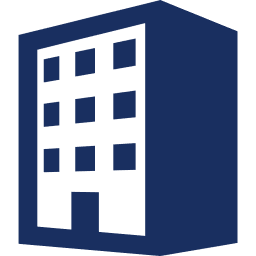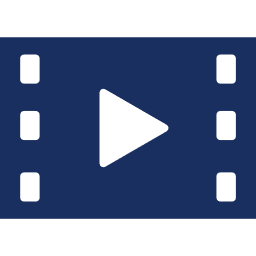途中乗車オーライ
私が小学1年生の時、母は東京で具合が悪かった股関節の手術をしました。母の状態が落ち着くまでの数年間は、母が担ってきた家のことを何とかしなければいけません。どういう経緯でそうなったのかわかりませんが、わが家に文江さんというお手伝いさんがくることになりました。お手伝いさんといえば、お金持ちの家かと思われるかもしれませんが、全然そういうことではなく必要に迫られてお願いしたのです。
文江さんは高知県立梼原(ゆすはら)高等学校を卒業したばかりで、18歳でした。文江さんは梼原に住んでいましたが、そこからだと遠くて通えません。そこで住み込みでお手伝いさんをしてくれることになりました。私は文江さんと遊ぶのが大好きで、いたずらもいっぱいしましたので、さぞ大変だったと思います。
私が通う小学校は、かなり家から離れており、バス通学をしていました。朝のバスは、当時すしづめ状態で、雨の日になるとさらに乗客が増えたため、降りたいバス停で降りられるか、不安で仕方ありませんでした。当時のバスはワンマンカーではなく、降りる時は車掌さんに「ありがとうございました」と言って降りた記憶があります。
定期券を忘れてしまったことがありました。これは子どもにとって大事件でした。「定期券を忘れました」と車掌さんに話そうとするのですが、うまく話せません。モゴモゴしていると、車掌さんが「どうぞ」と言って降ろしてくれたことを覚えています。
最大のバスの思い出は、毎朝の遅刻騒ぎです。年を取ってからは、早起きも苦にならなくなりましたが、幼いころは早起きが本当に苦手でした。しかし、バスに乗り遅れることは遅刻を意味します。当時、遅刻は重罪でしたから、何としてもバスに乗り遅れるわけにはいきません。毎朝がバタバタでした。
バス停は、家の路地を出たところから100mぐらい離れた場所にありました。この距離が小学生には遠いのです。目の前でバスが行ってしまったことも何度かありました。
やがて知恵がつきました。どうにも間に合いそうもない時は、文江さんに先に走ってもらい、バス停からちょっと先にある三差路の交差点で運転手さんに向かってお辞儀と合図をしてもらいました。そうするとバスの運転手さんがバスを止めてくれたのです。そこに、息せき切って追いついた私が乗るという具合です。今では絶対考えられないことですが、当時は、映画「三丁目の夕日」そのものの時代ですから、結構人情味があって、バスの運転手さんがバスを止めて私を待ってくれたのです。それを何回かやっていましたので、バスの乗客からは「またあの子が寝坊したよ」と白い目で見られていました。
お年寄りに席を譲ったこともバスの思い出の一つです。母が障害をもっていたこともあって、お年寄りに席を譲りたい気持ちが強くありました。しかし、小学1、2年生にとって、人に席を譲るという行為は簡単なことではありません。かなりの勇気がいります。私が席を譲ると、周りのおじちゃん、おばちゃんが私をジロジロ見て、「またあの子、席を譲ったよ」「幼いのに偉いねえ」などとヒソヒソ話し始めるのです。それが、とっても恥ずかしくて、しんどいなあと思ったものです。
それから2年がたちました。文江さんは二十歳を過ぎ、お見合いをして結婚することになりました。
文江さんがお手伝いさんを辞めて梼原に帰る日、私たちは駅のホームで文江さんを見送ることにしました。皆は、汽車の横で文江さんと別れを惜しんでいましたが、私は、1人ホームの端に行って、最後に手を振ろうと待ち構えました。
やがて、ホームに出発のベルが鳴ります。文江さんは私の姿を探しましたが見当たりません。汽車は走りだし、文江さんは窓から顔を出して私を探します。そしてホームの先端にいる私を見つけました。私は泣きながら思いっきり手を振りました。
それから半年後、文江さんは梼原町から南国市へお嫁にいきましたが、途中、私の家に立ち寄ってくれました。文江さんは町内の子どもたちにも大人気で、皆が文江さんの到着を待っていました。
やがて、白無垢(むく)姿の文江さんを乗せたハイヤーがやってきました。家の前は道が狭くて車が入れませんので、文江さんは近くの広場でタクシーを降りました。広場は、近所の人たちで黒山の人だかりができていました。
花嫁さんが車を降りると、ひときわ大きな歓声が上がりました。子どもたちは口々に「お嫁さんだ」「きれいだなあ」と言ってはしゃぎました。その場面は、「三丁目の夕日」そのものです。私は、文江さんがあまりにもきれいだったので、恥ずかしくて何も言えませんでした。
思えば、私は幼いころから、いろいろな人たちに守られ、育てていただきました。本当に「幸せだったなあ」と思います。