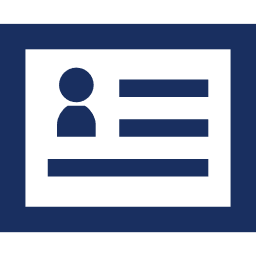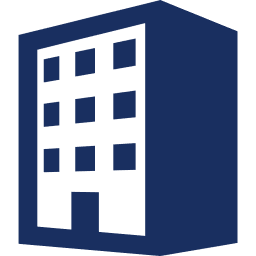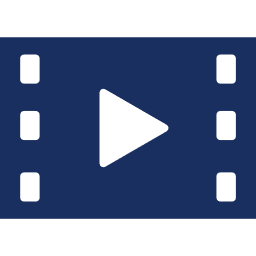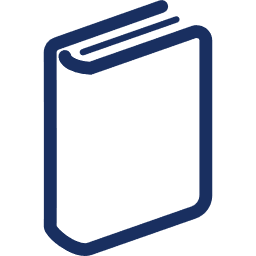プロセスが肝心
私は、「クレームは宝の山」であると認識し、クレームを「ラッキーコール」と称して、クレームに取り組むことでいい会社にする経営を実践してきました。ラッキーコールには3種類あります。お客さまからのラッキーコール、地域の人からのラッキーコール、そして社員さんからのラッキーコールです。
社員さんからのラッキーコールには、いわゆる苦情(不平・不満に起因する訴え)、クレーム(改善・原状回復・損害賠償などの要求)だけでなく、不安、悩み、相談、感謝などが含まれます。
この社員さんのクレームには、無言のクレームというものがあります。退職というクレームです。社員さんは辞める際、クレームを決して言いません。なぜ退職するのかを尋ねても、家庭の事情としか話してくださいません。しかし、こうした退職理由は本心ではありません。会社に対しての気遣いです。
会社は、社員さんから退職の申し出があってから苦情・クレームを解決しようとしても手遅れです。申し出た時点で、すでに次の会社を決めているからです。ですから、社員さんが退職したくなる前に、「ここで働きたい」と思っていただける会社にしないといけません。
とはいえ、私は、やみくもに離職率を低減しようとするのは間違いだと思います。そのようなことをしたらとんでもないことになります。社員さんの中には、問題行動を起こす人もいるからです。そういう人は会社にいてもらっては困る人です。
私は、経営者から相談を受けることがよくあります。あるとき、経営者さんから「こういう社員さんがいるのですが、どう対応したらいいのでしょうか?」と相談されたことがありました。私は「その人は会社にいてもらってはいけない人ですよ」とアドバイスしました。するとその経営者さんは、「えっ、でも人を大切にしないといい会社になれないんですよね?」と困惑されました。どうして、この経営者さんは困惑したのかというと、「人を大切にしないと、いい会社になれない」という思いが独り歩きしていたからだと思います。
「人を大切にする経営学会」というすばらしい団体があります。この団体は、社員等の満足度や幸せこそ最大目標であり最大成果と考え、「人を大切にする経営」を研究し、その研究成果を広く社会に還元・啓蒙する活動を行っています。
私がいうまでもなく、「人を大切にする経営」は、経営者なら目指すべき崇高な理念です。しかし、どんなにすばらしい理念でも、やみくもに導入すべきではありません。経営理念や行動指針が、自社にしっかり浸透していることが大前提です。何を目指して、何をするのかが不明確では、社員さんもどうしたらいいのかわからず、結果、「人を大切にする経営」はできないと思います。例えば、トップが「ワールドシリーズの優勝を目指す」と宣言すれば、その目的と目標に共感する選手が集まりますが、「スポーツチームをつくる」などとあいまいな宣言をしたら、野球をしたい人もサッカーをしたい人も集まってしまいます。野球チームなのにサッカーをしたい人まで入れて、すべてのメンバーを大切にしようとしたら、もはやチームが成り立たなくなります。「人を大切にする」という理念は、経営理念に共感する人たちであることを前提にした話だと思います。私に相談した経営者さんは、こうした前提を抜きに「人を大切にしないといけない」と考えてしまったようです。
経営者がやるべきことは、一にも二にも経営理念(目的・目標・手段)、行動指針などを明確にして、有言実行していくことだと思います。その結果、会社に合う・合わない人がでてくるのは、仕方のないことであり、むしろ自然なことだと思います。しかし、経営理念や行動指針などを明確にしていない状態で、会社を辞める人が続いていたとしたら、会社にとっても当該の社員さんにとってももったいないことだと思います。
私のメンターであり、ネッツトヨタ南国の取締役相談役である横田英毅さんは、社員さんに指示しない、教えない、社長の存在を消すといった経営をされています。かつて私は、横田さんの経営に非常に感銘を受け、自社に採り入れたことがあります。しかし、なかなかうまくいきませんでした。
横田さんには、その経営に至るまでのプロセス(過程)があります。そこをすっ飛ばして、いきなり結論だけを自社に採り入れようとしてもうまくいきません。私の会社にも、独自のプロセスがあって、「クレームは宝の山」に至っています。耳の痛いクレームと真摯(しんし)に向き合い、傾聴することでいい会社にしてきました。社員さんの話を表面的に聴くのではなく、背景にある事情まで聴いていくことで、見えなかったものが見えてきます。いい会社にする糸口が見えてくるのです。新しい理念や手法を導入する場合は、これまで築いてきた経営の土台と調和させる必要があると思います。
いまでこそ、このように話していますが、若い頃は、社員さんから苦情・クレームを受けると「そんなに嫌なら辞めてまえ」と腹を立てていたものです。もう少し早く、今のような経営手法が確立できていたら、前職の会社はもっとよくなっていたと思うといささか心残りです。